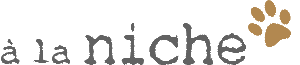今日は犬たち4匹をペットクリニックへ連れて行って、フィラリアの予防接種をしてもらった。

フィラリアの予防薬といえば昨年10月に本邦の大村教授がノーベル賞を受賞された発見のまさにそれそのものがその薬となっていて、ウチの犬たちは実際フィラリアに罹ったこともあるのでその有り難味もひとしおなのであるが、それが土壌中の微生物(放線菌)の産出する物質より作られるということで、炭素循環農法の主役であるところの土壌中微生物(放線菌や糸状菌)は一昨年来まさに自分の興味の中心の1つであったので、何とも不思議なご縁を感じずにはいられない。
ペットクリニックではついでに検査もしてもらった。全員問題無し。4匹もいると値段もバカにならないが、命の値段だと思えば全然安い。 ^~T(半泣)
だからというわけでは無いけれど、今日は天気も良く時間も少しあったので、昨年ジャガイモを植えていた畑を耕して炭素循環農法二期目のスタートを切った。

昨年ジャガイモを植えていた畑
昨年後半は事情で畑仕事がほとんど出来なかった。本来なら、自然の摂理に従って冬前に炭素資材を投入しておくべきところだったが、何もせず放置してあった。とりあえず、畑に生えた草も一緒に漉き込みながら表層プラスアルファを耕した。表層の下には白い線状の糸状菌が回っているのが見えた。

雑草も一緒に漉き込みながら耕す

少し掘り返すと糸状菌が回っているのが見える
今現在も微生物についての本を読みながらその奥深さに益々混迷を深めているのだが、微生物とか酵素の働きは本当に興味が尽きない面白い分野である。
・・・・・
これは覚え書きとして書いておくのだけれど…
炭素循環農法では土壌中微生物の働き方として、糸状菌や放線菌による有機物の好気下での発酵は、嫌気下での腐敗とははっきり分けて善悪として考えられる。
大雑把なところで、一概には言えないが一般的には【炭素→炭水化物・糖質→発酵】と【窒素→タンパク質→腐敗】という様な分け方ができる様な気がするのだけれど、日本の代表的な発酵食品である味噌や醤油や納豆などは豆類であり、分類的にどちらかといえば後者のイメージが強い。実際、炭素循環農法では窒素を固定化する豆類の栽培は別枠で考えられる節もあるのだが、これ如何に。