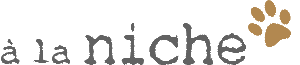この犬小屋には薪ストーブがあって、冬の暖房はこのストーブのみで賄っているので、ひと冬に結構な量の薪を消費する。
住宅団地の中の自宅の庭にも”初代犬小屋”があってそこにも小さな薪ストーブを置いていたのだけれど、そのときは小屋も薪ストーブも小さかったし、隣に本宅があるので薪ストーブはどちらかといえば趣味の範囲を超えるものではなくて、薪の消費量もたかが知れていたので近所のホームセンターで薪を買っていた。今の小屋は実質的に生活の拠点になっているので、本格的に薪の準備をしなければならなくなった。

初代犬小屋の薪ストーブ
こんな辺鄙な場所でも薪を用意するにはそれなりに結構苦労する。すぐ近くには薪屋さんがあったりするし、林業関係に伝があっても薪は大事な飯のネタの様なので無理も言えない。幸い、知り合いの解体屋さんが解体した廃屋の柱などを分けてくれるということになって、毎年のことでもあるし、メインはその様な手段で薪を確保することになった。ちなみに、解体した柱は針葉樹がほとんどで乾燥しきっているので燃費が悪いとは解体屋さんの語ったところで、その方も自宅で薪ストーブを炊いている。
とりあえず材料は確保出来たのだが道具も無いので、近所の人にチェンソーを借りて切ってみた。

チェンソーを使うのは初めてだったので恐る恐るではあったが、安全管理さえ徹底していればとくに問題なく作業は出来そうだ。
ただ、チェンソーは1日作業をすると切れ味が悪くなってきたり、潤滑用の油と混じったおがくずが中の方までこびりついたりするので、他の工具などに比べると頻繁に(使う度毎に)目立てや分解掃除などのメンテナンスをしなければならない様なので、早々に自前のチェンソーを用意することにした。
2シーズンほど使ってみて思うことなど
用意したチェンソーは、近所のホームセンターで長期在庫で割引してもらったハスクバーナの240eという型式のもの。ちなみに、このホームセンターでは現在この機種は取り扱っていない。というかメーカー廃番の様である。また、この機種の実質後継機種となるハスクバーナ 135eは一般向けで定価でも29,800円とリーズナブル。(ちなみに240eは定価オープンの実売5万円台。)ハスクバーナの高回転でモーターの様なエンジンはなかなかのお気に入りなので(山の中の遠くから聞いてもハスクの音は聞き分けられる様になった)、今あらためて買うとしたらこれを買うと思う。カタログスペック的にも240eとあまり変わらない印象。薪の玉切りくらいなら十分。ちなみに、240eでは最大80cm近く(ガイドバーが40cmなので切断可能な直径ほぼギリギリ)の切り倒したばかり(生木)の桜の株を切ったが、それなりに時間がかかるものの問題は無かった。職業として効率も考えなければならないなら大きな排気量が必要かもしれないが、薪の玉切りレベルでは持て余す。というか、林業の手元のバイトに行ったとき、本職の人もメインは小型のチェンソーを使っていた。
教訓:チェンソーは、大は小を兼ねない(オーバースペックは逆に非効率)。小でもそこそこ何とかなる。大には大の使い道。
目立てにはけっこうコツが必要な様で、角度などを決めるために目立て用のガイドもある様だが自分は使っていない。チェーンは右側と左側に歯が交互についていて、利き腕にヤスリを持って目立てをすると姿勢も変化するのでどうしても左右を均等に研ぐことが難しい。どちらか一方がキレが悪かったり、削り過ぎて短くなったりすると、丸太をまっすぐに切れず円弧を描く様な切り口となる。また、きれいに研げてなくて切れ味自体が悪い場合は切り屑がおがくずの様に細かくて粉っぽくなる。
最初はなかなかコツが掴めず、片方を削り過ぎて収拾がつかなくなって新しいソーチェーンを買い直すという様なことも何度かあった。
ここで人柱ポイント。
この機種の交換用ソーチェーンの型番が、互換商品も含めて近所で売ってない。
このチェンソーを買ったホームセンターにすら無いという・・・
仕方が無いのでその都度ネットで注文した。まぁ、結果的にはこの方が若干安く済んだかもしれない。でもこういうものは欲しいときにすぐに欲しいものである。また、ガイドバーなども消耗品の範疇に入るかと思われるが、こちらはネットですらなかなか見つけるのが困難である。
教訓 汎用性が高いたくさん売れてそうな国産モデルか、ハスクなど海外製なら現行品を選ぶべし。
近所のいちばん小さなホームセンターにも置いてある様な替え刃に適合する機種を逆算して選ぶというのも有りだと思う。
普段、取扱説明書などついぞ読んだ憶えが無いのだけれど、ことチェンソーに関しては動かす前に隅から隅までじっくり読んだ。また、チェンソー全般やこの機種についての情報を検索したりもした。
この240eというモデルはネット上の情報ではあまり評判が良くないらしい。
その原因は主にエンジンの不具合みたいである。なかなか始動しなかったりアイドリングがバラついたりストールするということが多い様だ。油まみれの切り粉が降り注ぐ悪条件の中で縦にしたり横にしたり斜めにしたりして雨の日も風の日も使われ、この小さなボディのエンジンとカバーの隙間に吸気排気燃料系の補機類や配管が所狭しと押し込められているのであるから、ちょっとした形状やレイアウトの設計的な差異も影響が大きく出るので、機種によって当たり外れがあるのかもしれない。
で、しばらく間をおいて2シーズン目に突入する際には、やはりこの問題が出た。
ここで人柱ポイントその2。
チェンソーは結構壊れる。
幸いというか、自分は若い頃に自動車整備の免許を取ったり仕事上もエンジン界隈の職についていたこともあったので自力で何とか対応出来たのだけど、毎回これでは先が思いやられる。
教訓 最低1回は修理に出すことを前提で、買う店や機種を選ぶべし。
これは実際、買う前にも悩んだポイントで、実は結構近く(車で5分ほどの所)に貴重ともいえるハスクバーナの正規取り扱いの販売・修理店があるのだけど、薪の玉切りごときで店に入るのは敷居が高いなと。ま、ホームセンターなら、何かあれば時間がかかってでも対応はしてくれるだろうと、そういう心情があった部分ではある。
現段階ではとりあえず事無きを得ているが、致命的な壊れ方をした場合にはやはり専門店で見てもらえる体制があれば、予備知識の収集も含めてそれに越したことは無い。
最後にもう1つの選択肢として、上記の135eの様な廉価モデルを使い捨て覚悟で選ぶというのも有りの様な気もする。自分で何とかする系の人は尚更であるが、壊れて元々と大胆に修理するのにも踏ん切りがつきやすいし、どうしようもなければ買い直すつもりで選ぶのも良いのではなかろうか。廉価版だからといっても機能や性能面で決定的なほどの差異は無い様に見えるし、今の自分ならやはりそちらを選びそう。
ま、クセも分かってきてそれなりに頼もしい240eとは、これからも長い付き合いになりそうなのだけれど。

(追記のこれマメ)
エンジンを良い状態に保つために、混合ガソリンを作る際のオイルは良いものを選べと本職の人が言っていた。メーカー純正が無難とのこと。自分は近所のホームセンターの高い方のやつを使っている。